クソ対応な乗務員の謎
事業場外みなし労働時間制は多様な働き方を実現できるか
氷河期おじさん 就職活動時代を語る
バス車内では絶対に転んではいけない
サヨウナラ、マツダ・アクセラ
クソ対応な乗務員の謎
先日、私の古巣のバスを利用したという方から乗務員の接遇がひどかったという苦情を受けた。私に言っても仕方がないのだが我慢ならなかったのだろう。私ははあはあ大変でしたねと適当な返事をしてその場をしのいだのだが、誰も見ていないだろうこの場でバス乗務員側としての言い分を書いてみようと思う。
バス乗務員は多様な人を相手にする仕事である。その相手は旅客に限られず交通社会の市民全般、つまり他車の運転手や歩行者なども対象となる。旅客以外の交通社会の当事者と接するときはだいたいろくでもないことなので最初から警戒心MAXなのだが、旅客の9割以上はまともな人だ。ただなにせ分母となる接する人の数が多いだけにヤバい奴に当たることも結構ある。
働いた親切には感謝で返されるのが当たり前だと思うし、人に親切にしたら感謝が返ってくることを期待するのは当然のことだろう。ところがヤバい奴は親切に対し文句を付け、罵声を浴びせ、またはさらなる要求を突きつけてきたりする。期待していたのと大幅に違う反応が返ってくることにショックを受ける新人乗務員は多いはずだ。
参考動画 うまく表示されない場合はコチラ
見返りを求めない仏のような人はひどい仕打ちを受けても施しを続けるだろうが、凡人たる大多数はそうではない。親切にしなければたとえひどい仕打ちを受けても耐えられると思うかもしれない。心の防衛本能というやつである。あるいは見返りがないのなら親切にする必要はないと思うかもしれない。最初は元気いっぱいでCS(Customer Satisfaction)表彰も受けていた新人乗務員が徐々に死んだ魚の目をして乗務するようになるのは、乗務員みな通る道だと私は思っている。
このようにして無愛想で不親切な乗務員は出来上がっていくのである。ただ会社に苦情を受け付けられると指導役から指導を受け鬱陶しい(もちろん評価にも響く)ので、苦情にならない、あるいは苦情の電話があっても乗務員が悪いとまではならないギリギリのレベルまで接遇レベルを下げてやろうと思う人も出てくるかもしれない。なんでそんなことをするか、シンプルに客(客側の人)が気に食わないからだ。理屈ではない。
例えば運転席で発車時間を待っているときにバスの時刻を尋ねられたとしよう。たとえ愛想が悪くてもバスを降りてバス停掲示の時刻表を元に説明をする乗務員は良い乗務員である。上記のようなギリギリを攻める乗務員は「時刻表はバス停に掲示してあります(棒読み)」「時刻はお客様ご自身でご確認の上ご利用ください(棒読み)」などといった応対だけしかしない。客にしてみたらひどい対応なのだが、何ら間違ったことは言っていないので苦情の電話があったとしても指導役も困ったなというだけで終わるだろう。乗務員経験のある指導役なら「お客様には親切にしましょう」という言葉がいかに空虚で相手に響かない言葉かよくわかっているはずだ。
もう少し経験を積むと選球眼が養われてくる。要するに良い客と悪い客との見分けが付くようになってくる。単純に良い(と判断した)客には親切にするし、悪い(と判断した)客には最低最小のことしかしないようになる。乗務員にひどい対応を受けたときは、自分に悪い客とフィルタされる要素はないか見直してみるのもいいかもしれない。また、バスの客となるときは自分は喋る荷物程度にしか思われていないと心得ることがお互いに不幸にならないのではないかと思う。運賃を払っている立場なのにけしからんと思う方もいるかも知れないが、そんな事を言っていられる時代ではなくなっていることをそろそろ自覚しなければならない。
ここでいうことはすべて私の体験談であり、ばす乗務員はみなこうであるとかいうつもりはもちろんない。ただ、以前はクソな対応の警察官にあたったときはシンプルに腹が立ったが今では日々社会の汚い部分に接し続けているわけだからこうなっても仕方ないかなと思うようになった(腹が立たないわけではない)。
このようなことを長々と書いて何が言いたいかというと、私は誰にでもニコニコと接することができる「出来た人」ではないということである。
(2024.5.2) ホームページに戻る
事業場外みなし労働時間制は多様な働き方を実現できるか
去る4月16日に「事業場外みなし労働時間制」に関する最高裁の判決が出た。
「事業場外みなし労働時間制」(労働基準法38条の2第1項)とは、事業場の外で労働しており労働時間の算定が難しいときは所定労働時間(8時間以下の就業規則で定める所定労働時間)労働したものとみなすことができる制度である。これ自体に労使協定の締結や労働者の同意の取得などは不要だが、労使協定の締結により通常必要な労働時間を定めることもでき、たとえばその時間を9時間と定めたならば毎日1時間残業(時間外労働)をしたものとみなして賃金計算を行うこととなる。
今回は過去に出された「阪急トラベルサポート事件」(最判H26.1.24)と解釈が変わるかどうかという点が注目されたが、結果として破棄差戻しという結果とはなったけれど法令の解釈自体に変更はないというもので、そのへんは判決の翌日に爆速公開された弁護士伊山正和先生のYouTubeを御覧いただければよくわかると思う。
私の私見として、裁判所としては法38条の2第1項を死文化させるつもりはないということを示したことがポイントではないかと思う。「阪急トラベルサポート事件」以後は、もう事業場外みなしは怖くて使えない、負けたらとんでもない額の未払賃金を払わなければならなくなるといった雰囲気があった。
結果として、外回りの営業マンなどはかつては事業場外みなしを使うのが当たり前というふうだったと思われるが、今は危ないのでやめましょうという感じとなっている。営業車をGPS管理すれば容易に労働時間管理ができるのだから、それをしないほうがおかしいのであって出来ることをしないのがいけないというのがその理由であるが、今回の判決では技術的に可能なことをしないことをもって直ちに会社の落ち度とはせずに、あくまで個別に検討するものとした。
よって、例えばGPS管理をしないのは営業マンの裁量に委ねるのを会社の方針としているからというのは、理由として通りうるのではないかと思われる。逆の言い方をすると、直行・直帰をするときは上司の許可を必要としているのなら適用はできないものと考えられる。また、不当な動機、具体的には残業代を払いたくないことが見え隠れする場合は厳しく判断されるだろうと思われる。例えば、業務時間内では処理しきれないような仕事を割り振り、消化しきれない仕事は会社ではなく家でやるよう指示(黙示的な指示を含む)することや、夜間しか対応しない顧客を担当させているにも関わらず朝9時からの朝礼には出席を強制している場合などが該当する。「事業場外みなし労働時間制」は残業代削減ツールではないのである。
コロナ禍を期に在宅勤務など多様な働き方が広まったが、労働時間をどう算定するかという点で課題があった。今回の判決は会社が緩やかな管理に留めるような働き方の普及促進には追い風となるだろうし、裁判所もそれを意識しているのではないかと思われる。
労働者の自由な働き方を認めるための制度として裁量労働制があるが、実態として残業代削減ツールとして悪用されまくったために年々導入へのハードルが上がっている。その点、事業場外みなし労働時間制は労使協定無しで始めることも可能なため、前提として働く場所が事業場外であることという制限はあるものの、今後普及していくかもしれないなと思っている。
労働者側としては、この制度によって算定された労働時間が実態より少ないが交渉をするのもなという場合は、簡単な話として会社に出てタイムカードを押せば良いので、一応対抗手段はある。それが難しいなら(要らないと言われても)上司に始業終了報告を記録が残る形でするとよいだろう。
なお、私がかつて働いていた会社は事業場外みなし労働時間制を準用し残業代を払っていなかったが、労基署から是正指導を受けている。直行直帰はできなくはないが上司の承認が必要なのでほとんどの場合会社にいったん戻るから、出退勤時間について事業場外みなし労働時間制を適用するのは無理がある。タイムカードはなかったので監査ではパソコンのイベントログをチェックして現実の労働時間を算定したという。
その後、会社はどうしても残業代を払いたくないので今度は1年単位の変形労働時間制を引っ張り出してきて、当社は絶対に残業代を払わないという決意みたいなものを感じ取ってドン引きしたのを覚えている。
ところで、自動車の運転の業務について規定する「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)では、「事業場外みなし労働時間制」の適用を認めていないことに注意が必要である。トラック、バスおよびタクシー運転手といった緑ナンバー車のドライバーは、乗務開始前後のアルコールチェックや点呼により始業・終業時刻が特定可能であり、運行中は常に運行管理者の指揮に服することとなっているため当たり前ではあるが、休憩時間についても実際に取ったかどうかにかかわらず一定時間を取ったとみなして労働時間から控除する取り扱いは違反となる場合があるため注意が必要である。
また、改善基準告示は白ナンバーの運転手、例えば社長お抱え運転手や幼稚園バスの送迎運転手も対象になりうるが、それらのものについても「事業場外みなし労働時間制」は適用できない。これらのものは自由な働き方とはなじまずむしろ会社の強い拘束を受けて働くべきものという考え方があるのではないかと考えられ、また改善基準告示により労働時間等について独自の規制がかけられているところ、事業場外みなし労働時間制の適用を許すと結果として改善基準告示適用逃れとなってしまい労働者の保護に欠けることになることが挙げられよう。
要するに運転手は「新しい働き方」とか「多様な働き方」とは無縁で、あるのは「多様な勤務パターン」だけということである。
(2024.5.1) ホームページに戻る
氷河期おじさん 就職活動時代を語る
国会議員の発言をきっかけに氷河期世代の苦労話が話題だ。その発言というのは、3月28日の参議院本会議で伊藤孝恵議員(S50年生まれ)が自身の就職活動時期に100社以上落ちたという話をしたところ他の議員から嘲笑された、という内容である。
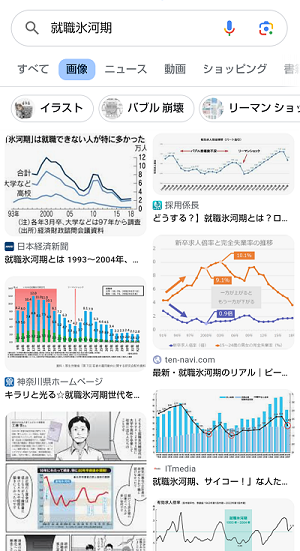
就職氷河期と言われるのは主に1993年から2005年に学校を卒業した者が特に就職に苦労したことから名づけられている。私は2000年卒でちょうどその範囲に入るのだが、前の年の先輩の惨状を目の当たりにした結果土俵に上がること自体をやめ、ろくに就職活動をしないまま卒業した。同級生が就職活動でヒイヒイ言っている間私は遊んでいたわけだ。
しばらくは学生時代から世話になっていたアルバイト(Wワーク)を続けていたが、ほどなく宅配ピザ屋のバイトは店ごと閉店してしまい、また当時安定の国営だった郵便局の深夜バイトは採算悪化でシフトを削るという話となり従来の収入を得るのは難しくなった。そうした中で就職情報誌を見ながら適当に履歴書を送って得た運送業の事務の仕事(3か月後に正社員登用、だったかな?)に就いたが、そこがとんでもないブラック企業で、結局1か月でクビになってしまった。
郵便局では社会保険に加入できたが雇用保険に入ったのは大学を卒業してからなのでわずか3か月程度では受給要件を満たさず、やぶれかぶれでいま思い返すと無鉄砲すぎるのだが、学生時代からやってみたいと思っていた北海道での長距離滞在を実行に移したのだ。
まずは礼文島にある桃岩荘ユースホステルに1週間ほど滞在しながら長期滞在のための様々な情報を得、紆余曲折を経て富良野市の農協のバイトの職を得ることができ(時給は確か900円と当時の北海道の相場よりかなり良かった)、当時長期滞在者の巣窟と化していた鳥沼公園キャンプ場(閉鎖済み)に格安の居を構えた。そこでバイトをしながら小銭が貯まるとバイクで北海道各地に走りに行って、このまさに現実逃避の日々はとても楽しく今でも懐かしく思う。しかし北海道の夏は短く、収穫が終わって農協のバイトも終了し、ちょうど貯金も食いつぶした頃に戻った。
金がすっからかんだったので市役所に生活保護を受けたいという相談をしに行ったら、少し前までバイクで遊んでいたようなやつが保護を受けることが出来るわけがないだろうと言われるも、生活再建のための10万円の無利子融資を受けることができ、また以前働いていたピザ屋の社員さんのつてで系列店でフルタイムのバイトで使ってもらえることができ、なんとかホームレスになるのは免れることができた。
ただ、ピザ屋のバイトは時給がいまいちであったので生活は厳しく、ふたたび就職しようと試みた。前回は就職情報誌で痛い目を見たのでハローワークなら大丈夫だろうという特に根拠のない考えでハローワーク通いを始め、ほどなくパソコンが使えるのならと紹介してもらった小さなシステム会社への就職が決まった。
その会社には大変お世話になったのだが、社長から、あてにしていた助成金がもらえず雇って損をしたと言われたときは大変困惑したものだ。当時は、氷河期対策として既卒者を雇用すると助成金が出たようだが、どうやらアルバイト時代の雇用保険加入歴を理由に不支給となったらしい。当時はアルバイトを社会保険に加入させるのは一般的ではなかったため、正社員になったことがないのに雇用保険に入っていたとは思わなかったのだろう。
とはいえ、助成金不支給を理由にクビにはならなかったし、おかげで向こう15年ほどシステムエンジニアとしてやっていく基礎となったので、当時の社長や上司には感謝しているし、雇用のきっかけとなった助成金制度にも感謝している。3年も経たずにやめてしまったのは今思うと本当にもったいなかったのだが、それはまた別の話である。
(2024.4.4) ホームページに戻る
バス車内では絶対に転んではいけない
先日所要で珍しくバスに乗ったのだが、その運転手が「止まるまで席を立たないように」とバス停が近づくたびにアナウンスし、また「万が一転ばれるとお怪我がなくても運行は中止となる」とまで言っていた。率直な感想として煩くて鬱陶しく、快適な車内環境とは程遠い。しかしその運転手さんがなぜそのような行動を取るようになったかは元バス運転手としてはもちろんよく分かるので、まあどちら側も幸せにならん話だよな、などと思った。

バスで転倒事故が発生すると運転手の責任になることがあることを知らない人はまだまだ多いようだ。電車の運転士に対してはそういうことはないのにバスだけおかしいという言い方もされていたりするが、それはちょっと違って、電車の運転士も故意または過失により客に怪我させるような運転をすれば刑事責任を問われうるし、免許も取り消される場合もある。ただ、急停車になるような場面はバスに比べればとても少ないしそもそも電車は急に止まれないので急停車だけで客が吹っ飛ぶようなことはあまりないだろう。また、最悪免許が取り消されたとしてもそれは電車の免許であり自動車の運転免許への影響はないので、仕事に就くことが困難になるまで追い詰められることも少ないのではないかと思われる。
バスのブレーキはよく効くので、ちょっと強めのブレーキでもどこにも掴まっていない立ち客は転んでしまう。またちょっと強めのブレーキをかけることはよくあって、その原因は飛び出してきた自転車だったり急に止まった前走車だったりさまざまである。自転車の飛び出し一つをとっても予見不能なものもあれば通常の注意力であれば気づくことができたものが何らかの理由で気づくのが遅れたという場合もある。
上記で挙げたうち、運転手の過失とされるのはもっぱら運転手の不注意によるものや操作ミスによるものである。他車の急な割り込みがあった場合などは処分に至らないだろう。一昔前は相手車がそのまま逃げてしまうと立証できないこともあったと聞くが、今ではドライブレコーダーがあるのでその点は良くなった。
また、停止寸前の衝動も厄介だ。これは運転手のブレーキ技術が未熟であるためによることもあるが、バス車両のくせによるところもある。また丁寧に止まろうとするとどうしても余分に時間がかかってしまうので、特に遅れているときはショックなく止める方にまで気が回らないこともある。また、立ち上がろうとするときは体のバランスを崩しやすいので、停止寸前に転ぶ事故は多い。この場合は乗客の怪我の原因は運転手の操作ミスとされ、もっぱら運転手の過失として処分されることが多い。
走行中のバスの乗客が転ぶなどして怪我をした場合は交通事故として取り扱われ、刑事・民事・行政上の責任を追う。怪我が軽微であっても「過失の程度」によっては運転手は罰金刑になるかもしれないし、免許停止処分を受けるかもしれない。免許を停止されるとしばらくは乗務ができないため収入の一部または全部を失うことにもつながる。
ただ、毎日十何時間もの乗務中ずっと注意力を維持するのは無理なので、会社は「立っている客全員が掴まっているか確認しろ」とか「立ち上がらないようこまめにアナウンスをしろ」と指導するわけである。実際に転倒事故があったときに、実況見分をした警察官がドライブレコーダーの映像を見て、運転手さんが何度も立ち上がらないよう言っているのに立ち上がって転んだんだからこれは客が悪い、とお咎めなしで済んだことも少なくない。かくして、冒頭で紹介したような運転手も出てくるわけだ。
また、これは地域差があるのかもしれないが、私が働いていたときは客が転んだときはそれが軽微で怪我がないと本人から申告があっても、その後の運行は中断し警察を呼ぶこととなっていた。その時点で怪我がないと申告があっても実は骨にヒビが入っていたという事例はよくあって、その場合運転手が救護措置を適切に取らなかった(いわゆるひき逃げに準ずるもの)のではないかという非常に面倒な話になることを避けるためである。
何にしても、転倒事故はおおごとであって万が一転んだ客となってしまった場合は他の客からお前のせいで遅刻だなどといった憎悪の眼差しを向けられるのは必至なので、バス車内では急に止まっても転ばないように想像力を働かせて行動するのが身のためである。
転んだのは客の自己責任ということにすればいいという意見も見られるがこれには賛同できない。客の自己責任で済むなら別に丁寧な運転をしなくてもいいわけで、折しも外国人労働者の受け入れ拡大もあいまってバスは安全な乗り物という地位を失うだろう。
(2024.4.1) ホームページに戻る
サヨウナラ、マツダ・アクセラ
2018年にマツダ・アクセラ(2.2lディーゼル仕様)を買って5年半ほど乗っていたが、バス会社を辞めるのを機に売却した。

大変いいクルマで、余裕の性能であちこちお出かけするのに使うかと思われたが、その2年後にバイクを買い替えてあとは遠出はバイクばかりになったので結局通勤ばかりに使用していた。通勤にはオーバースペックであり、3年目からは自動車税もエコカー減税なしの45,000円かかるようになったので負担感が増していった。折しもコロナ禍で収入はだいぶ減ってしまったので軽自動車に乗り換えようかとも思ったが、乗り換えの金を捻出することも難しく結局バス会社を辞めるまで使い続けた。
バス乗務員は電車の動く前から仕事を始めて終電後に帰宅するのでマイカー通勤になるのは仕方がないのは承知していたことだが、なぜかバイク通勤が禁止されているので維持費の安いバイクにすることもできなかった。
ディーゼル車はパワフルであり燃料代が安いのはよかったが、バッテリーが高いとか燃料フィルターの交換が必要とかガソリン車よりも色々金がかかるのが気になった。走行距離が5万を超えたあたりから燃費も落ちてきて、マツダのディーゼル乗りがいつか直面する排気系統の詰まりが顕在化しつつあるとは思っていたが、最後まで見ないふりをした。
今回は乗り換え無しの純粋な売却なため、一括査定サイトで査定依頼を出した。うちの一社から「入札形式にしてはどうか」と提案を受けた。なるほど入札であれば売る側も買う側も手間はかからなさそうである。交渉を重ねて1円でも高く売る、ということはできなくなるが、面倒なので入札で決めることにした。
指定の日時に3社の担当者がやってきて順番にクルマを見ていく。どうやら同業同士顔なじみのようで、車台番号の確認などは一緒に読み上げたり協力する様子が見られた。一方で一社の担当者が目ざとく見つけたキズ情報は連携しないなどライバルであることは間違いない。
買取価格提示は見積書で出したり名刺の裏に書いたりバラバラだったが、3社から受け取った時点で私が読み上げ、落札業者確定である。私は面倒なのでしなかったが、オークション形式で2番札3番札を出させる人もいるらしい。負けた各社は負けたという証明のためと各社の札を並べて写真に収めたあと光の速さで退散していった。なお、トップのドベの差は2万円も離れておらず不安を覚えるような査定結果とは思われず(異様な高値を提示し現車を回収したあと色々難癖をつけ払いを渋るなどは某BM社の件をきっかけによく聞かれた話だ)、また事前の想定をやや上回る価格だったので、こちらとしても満足である。
意外だったのが、3社来て誰も車検証読み取りアプリの入ったスマホを持ってこなかったことである。電子車検証に変わって当面の措置としてチップに入った情報をプリントした紙が交付されるが、なんの変造対策もされていない紙なのでそればかり見ていて大丈夫かと心配にはなった。
何にせよ金食い虫をようやく処分できて(毎月7,500円の駐車場代の支払いも不要になる)、身軽な形で新生活を迎えられそうである。
(2023.12.20) ホームページに戻る
Copyright 2024 Bocchi Sharoshi Office All Rights Reserved.